千葉県暴力団排除条例を後ろ盾とした暴力団に対する基本的対応要領
条例では、暴力団に対し、積極的に利益を与えるような行為などを規制しています。
これらの規制は、県民や事業者の皆さんが暴力団からの不当な要求を断る際の後ろ盾となるものです。
皆さんのほとんどが
- 「自分は暴力団とは関りがないから大丈夫だ。」
暴力団から不当要求を受けた場合、大切なことは、一人(一企業)で悩まず、警察や(公財)千葉県暴力追放運動推進センターなどに早期に相談することです。
県民や事業者の皆さんが、暴力団から不当要求を受けたときの対応要領について整理しました。
この対応要領に基づき、また、条例を後ろ盾として、不当要求を断固拒否し、社会全体での暴力団排除を推進するとともに、暴力団のいない千葉県を実現しましょう。
暴力団が恐れているもの、それは、あなたの
- 暴力団を恐れない「勇気」
まずは、平素からどのような準備をしておくとよいのか、4つのポイントをご紹介します。
1.トップの危機管理

2.体制作り

3.暴力団排除条項の導入

- 「暴力団とは取引しないこと。」
- 「取引開始後に判明した場合解約すること。」
4.警察等との連携

警察や(公財)千葉県暴力追放運動推進センター、弁護士などとの連携を保ち、事案発生に備え、担当窓口を設けておく。
不当要求対応要領12か条
「不当な要求には絶対に応じない」
という確固たる信念のもと、毅然とした対応をとることが大切です。
これからご紹介する「不当要求対応要領12か条」を最大限に効果を発揮させるには、大原則として、
「組織的な対応」
であることが、求められます。担当者が、個人的に対応したり、担当者のみに責任を押し付けることは最も避けるべきです。
不当要求に対しては、対応の方針を事前に検討し、組織として一丸となって対応することが何より大切となります。そのためには、危機管理意識をもって普段から「心と物」の準備をして有事に備えておくことが必要になります。
それでは、皆さんの家族や従業員などを守るために、「不当要求対応要領12か条」を参考に、具体的どのように対応するべきかご紹介します。
1.来訪者のチェックと連絡

受付や窓口を担当されている方は、落ち着いて来訪者の氏名や所属団体名などの確認と用件及び人数を把握して、対応責任者に連絡しましょう。
確認できない場合は、面談をお断りしましょう。
2.相手方の確認と用件の確認

対応者は、相手(複数の場合は全員)の住所、氏名、所属名、電話番号を確認し、相手の用件の確認を行います。
相手は「誠意を見せろ」「責任をとれ」などと遠回しな言い方をしますが、金銭的解決を前提とした交渉は禁物です。不当要求であることをはっきりさせるために、要求内容は相手側から、明確に言わせるようにしましょう。
3.対応場所の選定

素早く助けを求めることができ、精神的に余裕をもって対応できる場所(自社の応接室など)や管理権の及ぶ場所を選びましょう。
暴力団事務所など相手の指定する場所に出向くことは厳禁です。
4.対応人数

不当要求の手口は、脅して正常な判断を奪い、そこにつけ込むというのが常套手段です。相手方より優位に立つための手段として、必ず相手方より一人でも多い人数で、かつ各人の役割分担を決めて対応しましょう。
-
- 責任者:主に対応します。
- 録音係・記録係:言動や相手の特徴を記録します。
- 連絡係:外部との連絡をとります。
5.対応時間

応対している時間が長いと、相手方のペースにはまる危険性が大きくなります。
あらかじめ「〇時から会議があるので時間を〇分と区切らせていただきます。」などと告げて対応時間を明確に示しましょう。時間になったら明確に打ち切りの意思表示をしましょう。
6.言動に注意する

不当要求に対しては、あいまいな言動や安易な妥協は禁物です。
粘り強く、慎重に言葉を選んで、筋の通った対応としましょう。
特に暴力団は、巧みな論争により対応者の失言を誘い、又は言葉尻をとらえて厳しく糾弾してきます。「申し訳ありません。」、「検討します。」、「考えてみます。」等は禁物です。
7.書類の作成・署名・押印

「一筆書けば許してやる。」などと詫び状や念書を強要してきますが、絶対に書いてはいけません。「非を認めた」としてさらに要求がエスカレートすることもあります。
また社会運動に名を借りて署名や押印を求められることもありますが、紹介者・代理人として悪用されることが考えられますので、決して応じてはいけません。
8.トップは対応させない

本社・支店のトップなどの決裁権を持った者が対応すると、即答を迫られ、以後の交渉もトップが応じるよう強要されがちです。ただし、多忙を理由にすると居座り、居留守がわかると脅しのネタにされかねないので、あらかじめ担当者を決めておきましょう。
要求内容を社内で検討し、警察等に相談することも考慮して余裕を持って判断できるようにしましょう。
9.即答や約束はしない

相手の要求に即答や約束をしてはいけません。暴力団員は、企業方針が固まらない間が勝負の分かれ目と考え執拗に、その場で回答を求めてきます。
10.湯茶の接待はしない
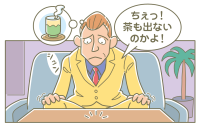
湯茶を出すことは、暴力団員が居座り続けることを容認したことになりかねません。また、湯飲み茶碗などを投げつけるなど、脅しの道具や凶器に使用されることがあります。
11.対応内容の記録化

電話や面談の対応内容をメモすることは、犯罪検挙や行政処分、民事訴訟の証拠として必要です。
また、「お話の内容を正しく上司に報告するために録音させていただきます。」などと相手に明確に告げて、録音、撮影をしましょう。脅しのトーンも記録でき、相手の行動を抑制するという効果があります。
12.機を失せず警察に通報

相手が居座り、退去を求めても応じなかったり、暴行を受けた場合は迷わず、恐れず躊躇せずに、すぐに警察に通報しましょう。
不要なトラブルを避け、受傷事故を防止するため、平素から警察や(公財)千葉県暴力追放運動推進センターとの連携を心がけることが早期解決につながります。
| お問い合わせ |
| 千葉県警察本部 組織犯罪対策課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |


